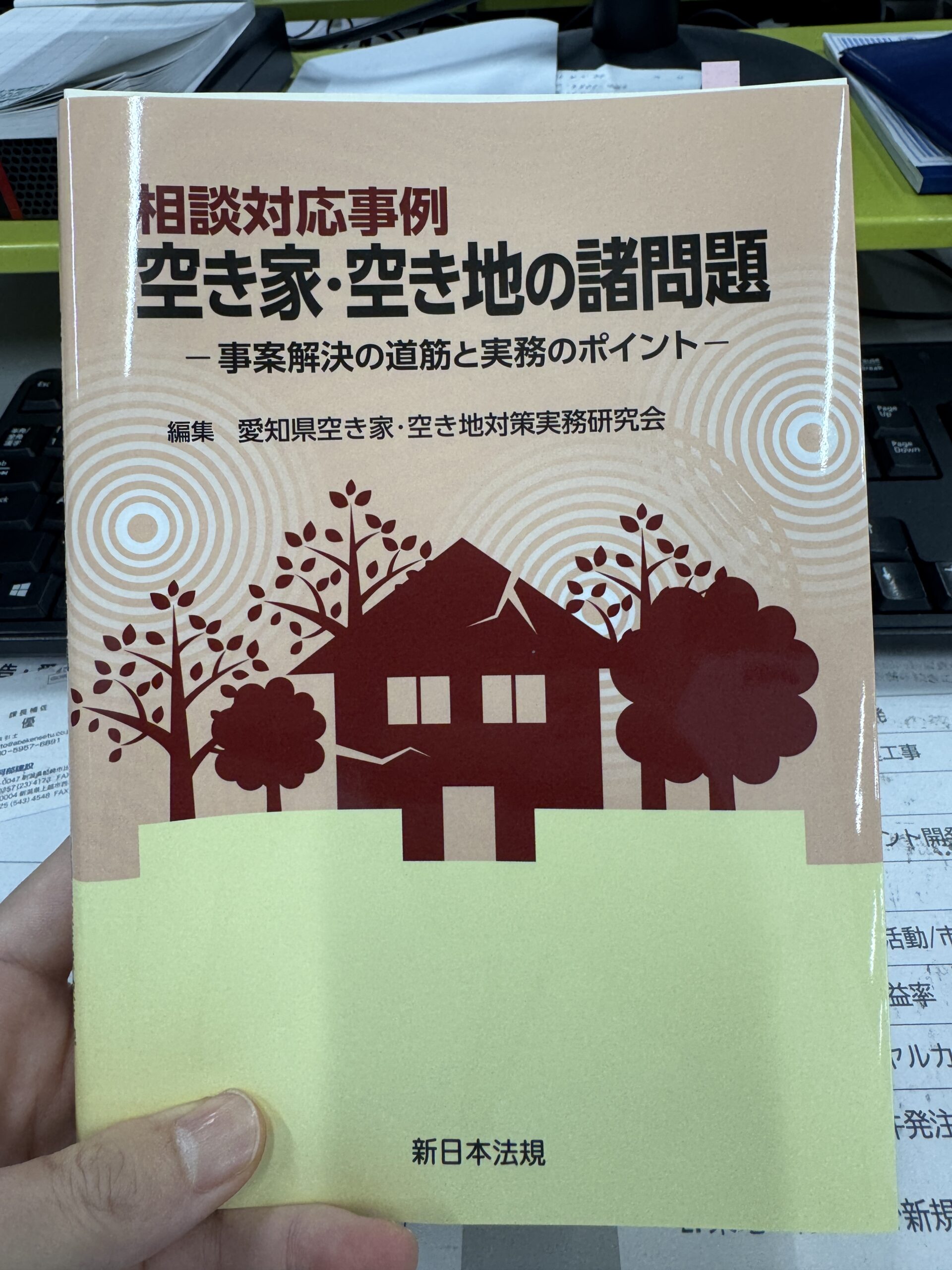田舎古民家の「誤算」と、その後の風景
昨年末、私の元には空き家の売却相談が相次いでいたが、
その中の一軒が、この電波の届かぬ場所に建つ立派な古民家。
聞けば、現在の所有者がこの物件を購入したのは、わずか一年前のことだという。
一見すれば「転売」か「投機失敗」を疑うような短期間での手放しだが、
その背後には、個人の力では抗えない事情があった。
その夫婦は、近くの自宅を子供に譲り、二人で余生を過ごす「終の棲家」としてここを選んだのだ。
しかし、入居を待たずして、ご主人が急逝。
残されたのは、200坪の広大な土地と、二棟の立派な車庫、そして主を失った古民家だけだった。
現地に立つと、たしかに景色は素晴らしい。
しかし、周囲を山に囲まれ、遮蔽物のない敷地を吹き抜ける冬の風は、
身体の芯まで凍えさせる「格別の寒さ」である。
建物内部は、驚くほど手入れが行き届いていた。
新調された畳の香りが残り、陽光が差し込む縁側は、
かつての夫婦の希望をそのまま形にしたような平穏さに満ちている。
だが、この「美しさ」と「立派さ」だけでは、今の地方が抱える課題は解決しない。
小学校の統廃合が進み、通学路という概念すら消失しつつあるこの立地で、
ファミリー層の定住を期待するのは、あまりに楽観的すぎるだろう。
ここは、「利便性のある郊外」ではなく、ただ、不便という現実が剥き出しになった「田舎」なのだ。
しかし、そこに絶望があるわけではない。
この不便さを「日常のノイズの遮断」と捉え直し、電波の届かない静寂や、
際限のないDIYを「贅沢な不自由」として享受できる層は、確実に存在する。
ただ空き家を右から左へ流すのではなく、この土地が持つ特異な条件を「コンセプト」として再定義すること。
それが、誠実な不動産売買のあり方ではないだろうか。
寒風に晒されながら、そんなことを考えもしたが、とにかく早く暖をとりたかった。